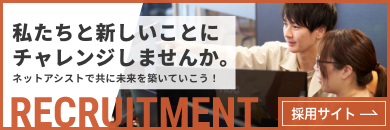もしものためにどこまで備える?ディザスタリカバリ構成について

こんにちは。Wです。
7月30日8時24分頃(日本時間)、ロシアのカムチャツカ半島付近でマグニチュード8.7の地震が発生しました。
日本では太平洋側を中心に、北海道から本州、さらには九州までと広い範囲で津波警報および注意報が発表され、実際に津波も観測されていました。
ほとんどのテレビ番組は飛び、津波に関する情報が速報で伝えられ、速やかに避難するよう呼びかけが繰り返し行われていました。
沿岸地域付近では、電車の運休や遅延も発生していましたね。
水曜日ということもあり、通勤や通学にも影響があったかと思います。
夏休み期間でもあるため、予定変更をされた方もいるのではないでしょうか。
東日本大震災の時には南米のチリでも津波が観測されたと言いますし、改めて自然災害の脅威を感じました。
落ち着いて適切な行動が取れるよう、自然災害への理解を深め、備えておく必要がありますね。
また、サーバーやサービスにおいては、日本での自然災害はもちろん、日本国外でもしものことがあった場合の影響も考える必要があるかもしれません。
そこで今回は、「ディザスタリカバリ」について、まとめていこうと思います。
備えあれば憂いなし と言いますし、特性や予算など現実的に考える部分もあると思いますが、参考までに紹介していきます。
ディザスタリカバリとは
ディザスタリカバリとは、「災害復旧」という意味です。
予め災害を想定し、物理的に離れた場所にそれぞれシステムを構築することで、サービスを継続提供できるようにします。
想定する災害の規模によって構成は異なり、被災地域の想定が首都圏であれば東京と大阪に設置、より広く日本全国であれば国内と海外に設置する場合もあります。
万が一災害が発生した際には、被災していない地域にある運用環境に切替えてサービス提供を継続します。
弊社HPでは、このような代表的な用語を解説しているページもありますので是非ご覧ください…
https://www.netassist.ne.jp/dictionary/dr/
弊社では、ディザスタリカバリを含む冗長化のご提案も可能です。
以前に紹介させていただきましたが、実際にAWS環境でご提案・構築をさせていただいたことがあります!
https://www.netassist.ne.jp/techblog/23800/
クラウドベンダーごとでリージョンの比較
簡単ではありますが、各クラウドベンダーのリージョンについて紹介します。
ベンダーごとでどのような違いがあるのでしょうか。
AWS
皆さまご存じの通り、世界各地にリージョンがあり、サーバーを立てることができます。
2025年8月現在、33のリージョンと105のアベイラビリティーゾーンがあります。
AWS Regions
https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/global-infrastructure/latest/regions/aws-regions.html
日本には、東京と大阪の2つのリージョンがあります。
・ap-northeast-3:Asia Pacific (Osaka)
・ap-northeast-1:Asia Pacific (Tokyo)
日本国内の2拠点を選択することも可能ですし、アメリカやアジア地域、ヨーロッパから南米も選択できます。
この点については、AWSの強みでもあるかと思います。
また、AWSには「AWS Well-Architected Framework」と呼ばれる考え方があり、ベストプラクティスに沿って構築することが推奨されています。
もしもの時の被害を最小限にすることやサービスの継続性について、提示されています。
さくらインターネット
ガバメントクラウドにも選定されたさくらのクラウドは、日本国内の東京と石狩にデータセンターがあります。
その中でさらに、それぞれ第1ゾーン・第2ゾーンがあります。
さくらのクラウドを選ぶ理由
https://cloud.sakura.ad.jp/feature/#02
GSLB(グローバルサーバーロードバランシング)を利用することで、複数のロケーションをまたいだ構成が可能になります。
IDCフロンティア
IDCフロンティアより提供されるIDCFクラウドは、東日本リージョン(福島白河データセンター)1,2,3と西日本リージョン(福岡北九州データセンター)があります。
その中でさらに、合計15のゾーンがあります。
リージョン・ゾーン
https://www.idcf.jp/cloud/spec/region_zone.html
こちらも、GSLBを利用することで、複数のロケーションをまたいだ構成が可能になります。
その他
また、「マルチクラウド」という考え方も広まりつつあります。
マルチクラウドとは、その名の通り複数(2つ以上)のクラウドサービスを接続し、組み合わせて利用することです。
前述したリージョンだけでなく、複数のクラウドベンダーを利用することで、ベンダー全体での大規模障害にも備えることができます。
こちらも以前に紹介させていただきましたが、実際にAWS環境+さくらのクラウド環境のでご提案・構築をさせていただいたことがあります!
https://www.netassist.ne.jp/techblog/33843/
まとめ
先にも書いた通り、構成の規模としては大きくなるので、その分費用はかかってしまいます。
しかし、ダウンタイムは最小限でサービスを提供する必要がある場合や機会損失を防ぎたい場合などは、非常に有効な手段かと思います。
また、クラウドサーバーのメリットとして、「柔軟性」があります。
スモールスタートからでも、冗長化やディザスタリカバリ構成など、拡大・縮小が可能です。
ぜひ気になることがあれば弊社までお問い合わせください!
それでは、また。